
ドラゴン:ヨーロッパ1
雑記帳:た行
「ヨーロッパ1」ではキリスト教のドラゴンを扱います。何となれば、以降の全ヨーロッパ文化はキリスト教の影響無しには考えられませんので重要ですね。
キリスト教というのも人によって(日本の話ですが)相当振幅のあるイメージが持たれている文化です。キリスト教徒とかじゃないかぎり、題材にした文物に触れることが多い割に直接『聖書』を読むことなんかはまず無いので、その触れたもの次第で結構極端なイメージになる。『ダ・ヴィンチ・コード』や『フーコーの振り子』とかでキリスト教に触れてる方達にはとんでもない秘密を抱えているものだ、ということになるでしょう(あるいは最近だと『エヴァンゲリオン』とかか?)。
確かにキリスト教に端を発する秘教・結社というのはあるんでして、それもまた一面ではありますが、そんなオドロオドロしたものが西欧中世を千年に渡って築いたわけじゃありません。オーソドックスなキリスト教というのは相当シンプルなものです。
ドラゴンにしてもですね、新約聖書の中核をなす福音書(マルコ・マタイ・ルカ・ヨハネ)の中には一匹も出てきませんね。せいぜい伝統と形式だけの形骸化した信仰の徒を指して「蝮(マムシ)の末」と言ったりしているくらいです。もうそういった神話的怪異で世界を記述する時代のものではないのですね(無論そういった部分を『旧約』としてあわせるという想定がはじめからあったからでしょうが)。
福音書
その福音書ですが、簡単に言いますとイエスが教えを始めて十字架にかけられるまでの事蹟が語られているものです。四つともそう。特にマルコ・マタイ・ルカはほとんど同じ内容です(なのでこの三篇は「共観福音書」と言う)。マルコに無い生誕話がマタイにあったり、ルカは文章が達者だったりとそのくらいの差。ヨハネの福音書だけは他に比べて少々神学論気味に毛色が違ってますが、追うストーリーは一緒。

洗礼を受けるイエス(ダ・ヴィンチ)
この「並び」は一応想定される成立順なんですが、確かにマルコ福音書とかは(文が朴訥なのもありますが)、相当素朴でして、「メシアのイエス」というより「ナザレのイエス」という感じです。全然秘教じみてはいませんね。
後にも詳しく述べますが、イエス自身が「教義の体系化」そのものを否定しているところがありますので、その「教え」というのも実態は相当「ぶっちゃけ」です(以下福音書からの引用は岩波文庫『新約聖書・福音書』塚本虎二訳より。無教会派の個人口語訳ですね)。
一人の聖書学者がこの議論を聞いていたが、イエスがあざやかに答えられたのを見ると、進み出て尋ねた、「どの掟がすべてのうちで第一ですか。」イエスは答えられた、「第一はこれである。−−"聞け、イスラエルよ、われわれの神なる主はただ一人の主である。心のかぎり、精神のかぎり、" 思いのかぎり、" 力のかぎり、あなたの神なる主を愛せよ。" 第二はこれ。−−"隣の人を自分のように愛せよ。" これら二つよりも大事な掟はほかにはない。」
−−−−−−マルコ福音書
だから、何事によらず自分にしてもらいたいと思うことを、あなた達もそのような人にしなさい。これが律法と預言書と(聖書)の精神である。
−−−−−−マタイ福音書
大体これだけですね(とか言うとこっぴどくしかられそうですが)。なんと言うかあらゆる虚像を認めないと言いますか、権威も儀式も階級も民族も「そんなことは知らん」というのがイエスです。人の作ったモノサシなど彼の知ったことではないのですね。おそらく今の教会組織の在り方がキリスト教だというイメージだと少々見当を外すでしょう(ま、どの宗教もそこは一緒ですが)。
それは他ならぬこの『福音書』を見ていくことで明らかになりますが、「ドラゴン」的にはちとしんどい(出てきませんから…笑)。大体…
あなた達は、地上に平和をもたらすためにわたしが来たと思うのか。そうではない、わたしは言う、平和どころか、内輪割れ以外の何ものでもない。今からのち、一軒の家で五人が割れて、三人対二人、二人対三人に割れるからである。父対息子、息子対父、母対娘、娘対母……
−−−−−−ルカ福音書
とかいきなりずらずらならんでも「えぇぇぇー」でしょう?
ということで、まずはちょっと下りましての黎明期に迫害を受けつづけたキリスト者達は、そのなかで殉教していった信者達を「聖人伝承」として語りつづけたのですが、彼らの逸話に出てくるドラゴン達を覗き、この頁の入口としましょう。
『黄金伝説』のドラゴン
以下に引用する『黄金伝説』の訳注によりますと、キリスト教の聖人伝承をひっくるめますとなんと30人からの聖人がドラゴンを倒すなり退けるなり手なずけるなりしているそうな。ドラゴン=悪魔であり、聖人とは悪魔の誘いを退けるものなのですからさもありなんという感じですが、全部あげていったらきりがない(笑)。ここでは次項で見る『福音書』の詳細につながる象徴的なお話を二つ紹介していきます。
どちらも13C中世ジェノヴァの大司教であったヤコブス・デ・ウォラギネ著による『黄金伝説』(全4巻 前田敬作・山口裕 訳 人文書院)という聖人伝承の集大成となる資料からのものとなります。
聖ゲオルギウス
騎士ゲオルギウスは、カッパドキアの出身である。あるときリビュアの町シレナに立ち寄った。町の近くには、海のように大きな湖があって、毒をもった竜が棲んでいた。町の住民たちは、武器をとって総出で竜を退治に出かけたが、そのたびに命からがら逃げ帰ってきた。その後、竜は、町の城壁の下までやって来て、毒気を吹きかけて悪疫を蔓延させた。そこで、市民たちは、やむなく毎日二頭の羊をあたえて竜の怒りをなだめていた。羊をあたえないと、竜は、町の城壁の下にあらわれて、毒気で空気を汚染し、多くの人たちがそのために死んだのである。けれども、羊の数がしだいに減り、調達も思うにまかせなくなってきたので、毎日人間ひとりと羊一頭を竜にあたえることに決まった。そこで、だれを竜に食わせるかをくじでえらんだ。だれもくじをまぬがれることはできなかった。こうして、町の息子たちや娘たちがほとんどみな人身御供にささげられたころ、とうとう王のひとり娘がくじにあたり、竜の餌食になることになった。
で、王が取り乱してすったもんだあるのですが、結局娘は王女として贄に供されることを受けます。
(王女は一人湖へむかった)
たまたまそこへ聖ゲオルギウスが馬で通りかかった。王女が泣いているのを見て、どうかなさったのですかとたずねた。
白馬の王子様ですな(笑)。いや、本当に白馬なのです(ゲオルギウスの象徴の一つは白馬)。で、王女はけなげにもゲオルギウスに逃げろと忠告する。
「親切な騎士さま、あなたを巻きぞえにしたくはありません。命を落とすのは、わたしひとりで十分でございます。と申しますのは、わたしを救うことなどとてもできるものではありません。あなたも、わたしといっしょに殺されておしまいになりますもの」王女がまだ話しているうちに、はたせるかな、竜が湖面から頭をもちあげた。王女は、恐怖のあまりふるえながら叫んだ。「騎士さま、どうかお逃げになって。はやくお逃げになって!」しかし、ゲオルギウスは、ひらりと馬にまたがると、十字を切り、こちらへ近づいてくる竜めがけて馬を走らせた。そして、長い槍をぐるぐる振り回し、神に加護を祈って、えいとばかりに竜に突きたてると、竜は、どうと倒れた。それから、彼は、王女にむかって、「腰帯をほどいて、竜の首に投げかけなさい。こわがることはありません」と言った。王女は言われたとおりにした。すると、竜は子犬のようにおとなしく王女のあとについてきた。こうして王女が竜をつれて町に帰ると、住民たちは、怖れおののいて、山や洞窟にのがれ、「たいへんなことになった。もうだれも助かる見こみはない」と嘆いた。そこで、聖ゲオルギウスは、彼らのほうに手をあげて、こう呼びかけた。「こわがることはありません。と言いますのは、主なる神は、あなたがたをこの竜から救うためにわたしをおつかわしになったからです。ですから、キリストを信じて、みんな洗礼をお受けなさい。そうすれば、竜を殺してあげます」この言葉を聞いて、王がまっさきに洗礼を受け、全住民も、これにならった。聖ゲオルギウスは、剣を抜いて竜を殺し、死骸を町からはこびだしなさいと命じた。
めでたしめでたし。しかしゲオルギウスはその手柄を自らのものとすることなく、あくまでキリスト者として立ち居振る舞います。
国王は、聖ゲオルギウスに莫大な財宝をお礼のしるしにさしだした。しかし、聖人は、これを受けず、貧しい人びとに分配させた。それから、王に教訓を垂れて、「あなたは、四つのことをお守りにならなくてはなりません。教会を保護し、司祭をたちをうやまい、熱心にミサにあずかり、貧しい人たちにいつも眼をかけてあげるのです」と言うと、王に別れの接吻をし、馬を駆って立ち去った。
ということでした。もともとこのお話はもっと古いころから(少なくとも11C以前から)あったものの様で、それはもっとシンプルなドラゴン退治だった様ですね。

聖ゲオルギウスとドラゴン(15C)
べつの本によると、聖ゲオルギウスは、竜が王女にとびかかろうとしているのを見ると、十字を切るなり馬もろとも竜めがけて突進し、一撃のもとに竜を退治したことになっている。
さて、もっともこれはゲオルギウスのエピソードの半分以下でして、この後に、拷問→殉教の殉教者としてのエピソードが続きます。
この時期が、ローマのディオクレティアヌスとマクシミアヌス帝のキリスト教大迫害の際のこととありますので、殉教は303年ころとされますね。いずれにしてもこのペルセウス=アンドロメダ型のドラゴン退治譚が人気でして、聖ゲオルギウスといったら並みいる聖人の中でも一二位を争う人気です。
聖ジョージが英語読み。地元カッパドキアの方では早くからこの物語が広まっていた様ですが、西でもフランク王国のメロヴィング朝が彼を祖とする伝説を採用したのを皮切りに、ロシア・ドイツ・イタリア各地でさまざまに守護聖人とされ、特にイギリスではリチャード一世(獅子心王・12C)が自らの守護精霊として仰ぎまして、はてはイギリス自体を保護する聖人とされます。イギリスの最高勲章ガーター勲章とはすなわち「セント・ジョージ勲章」ですし(14C制定)、イギリス国旗の赤色十字も彼の標章とされます(他にドラゴン、車輪、白馬、旗と楯など)。おもしろいのは10月27日が「ドラゴン退治記念日」なんだそうな(以上『黄金伝説』訳注より)。

ガーター勲章の装飾(本体は文字通りガーター)
これがいわゆる「聖ゲオルギウスの竜(聖ジョージのドラゴン)」の顛末です。ここでもっとも目を引きますのは、町へ竜を生かして連れてくる件です。なんでドラゴンが「子犬のように」おとなしくなったのかも今ひとつ謎ですが、それよりゲオルギウスの町の人への台詞が凄い。
キリストを信じて、みんな洗礼をお受けなさい。そうすれば、竜を殺してあげます。
信じなかったらどうなるのだ、これ(笑)。冗談みたいですが、結構ここがポイントです。つまり、ドラゴンをゲオルギウスが(彼の力で)倒す、というのがこのお話の眼目ではないのです。大まかの構造を取り出すと
町人がキリスト教の洗礼を受ける
→ドラゴンが消滅する
こういうものなのですね。先にも述べましたが、もともとは「べつの本によると」の様に、純然たるペルセウス=アンドロメダ型のドラゴン退治だったのかもですが、キリスト教の中で伝説化する過程では、お姫様の帰還はもはやどうでもよくなってます。ゲオルギウスもその「褒美」を受取らない。このドラゴンとは一体なんだったのか。
ドラゴン(悪魔)とは囁くものなのです。
何をか。「蛇の知恵」をです。
このドラゴンもゲオルギウスに「倒されるため」に出てくる。ドラゴンは町の人とゲオルギウスに囁いているのです。
ゲオルギウスに自分を倒させて彼をを王に戴け、と。
自分を倒して、お前が王になれ、と。
だからこそ、ゲオルギウスは倒さずに町に竜をつれてくる。額面通りとったらこれは単なる脅しです。キリスト教を選ばなければまた竜を放つぞと。しかし、そんなバカな話はない。そう見せないためには別に湖でドラゴンを倒し、それに感謝した町の人びとがキリスト教の洗礼を受けた、で良いはずです。何故、町へドラゴンを連れてくるのか。
ゲオルギウスはドラゴンの囁きを聞いてこれを自らの力で倒し、蛇の知恵、王になる知恵を選択するわけにはいかなかった。ドラゴンは「町の人びとがキリスト教化する=蛇の知恵を受け入れない」ことによって消える必要があったのです。その構造を成立させるためにドラゴンは連れて来られているとしか考えられない。
ここにキリスト教が「悪魔」によって示そうとしたコード、「王のコード」への考え方、処し方が表れています。後に見るように「悪魔の囁き」とは「王になれ」とほぼイコールです。それは、一見まったく別の物語に見えるもうひとつの殉教者のお話、ドラゴンを退けた聖女マルガレタのお話を考えることでも見えてくるでしょう。
聖女マルガレタ
マルガレタは、アンティオケイアの出身で、異教の神官テオドシオスの娘であった。乳母の手で育てられて、成年に達すると、洗礼を受けた。そのために父に憎まれた。十五歳のころ、ある日仲間の乙女たちと羊の番をしていたところへ、たまたま長官のオリュブリオスが通りかかった。彼は、マルガレタの美しさを見るなり、たちまち恋のとりこになり……
というわけでお定まりの「お代官さま」コース。んが、マルガレタ(マルガリタ)がキリスト者であることが引っかかり、談判破裂します。
(マルガレタが投獄された)あくる日、彼(長官)は、またマルガレタをつれてこさせて、言った。「おろかな乙女よ、おまえの美しさが惜しいではないか。しあわせに暮らせるように、われわれとおなじ神々を拝んではどうだ」彼女は答えた。「わたくしが崇拝するおかたは、大地もふるえ、海もおののき、風もあらゆる生きものも怖れかしこむおかたです」長官は言った。「言うことを聞かんのなら、八つ裂きにしてやるぞ」しかし、マルガレタは、「キリストさまは、わたくしのために死地におもむかれました。ですから、わたくしも、キリストさまのために死ぬことをいといませぬ」
で、「さすがの彼(長官)も、これほどおびただしい血をもはや正視していられなかったのである」というほどの拷問となり、それでも全く挫けないマルガレタは再度投獄されます。
牢獄は、たちまちふしぎな光に煌々と照らされた。彼女は、牢に入ると、わたしと戦う敵を眼に見える姿でおしめしください、と主に祈った。と、たちまち、一匹の巨大な竜があらわれた。竜が彼女めがけておそいかかり、あわやひと呑みにしようとしたとき、彼女は、十字を切った。すると、竜は、消え去った。異本によると、竜は、大きな口をあけ、上あごを彼女の頭のうえに、舌を足のしたにあてがって、彼女をがっぷり呑みこんでしまった。彼女は、竜の体内に入ると、腹のなかで十字を切った。すると、竜は、十字の印がもつ力のためにまっぷたつに破裂し、彼女は、傷ひとつ負わずに出てきたという。しかし、竜がマルガレタをいったん呑みこんだあと破裂したというこの話は、どうも眉唾もので、真実らしくないとおもわれる。
そこは真剣に疑問を呈すとこなのか、という気がしますが、案外こういったところが重要かもしれません。「竜に呑み込まれる」が何を意味しているのか、ということですね。
その後しばらくして、悪魔は、またぞろマルガレタをたぶらかそうとして、人間の姿に身をやつしてあらわれた。しかし、彼女は、その姿を見ると、ひざまづいて祈った。それから、ふたたび身を起こしてみると、悪魔は、そばに歩みよってきて、手をとると、「あなたがこれまでにしてきたことにみずから満足して、もうわたしから離れなさい」と言った。しかし、マルガレタは、悪魔の頭をつかんで、地面に投げ倒し、頭に右足をのせて、「高慢な悪魔よ、女の足にふんづけられているがよい」と言った。悪魔は、悲鳴をあげた。「おお、聖女さま、マルガレタさま。わたしの負けです。たくましい若者に負けたのなら、それもしかたがないとおもいますが、たおやかな乙女にうち負かされたとは、なんともだらしのない話です。あなたの父上と母上がわたしの仲間であるだけに、なおさら面目ないことです」マルガレタは、なおも痛めつけて、どんなわけであらわれたのか言いなさい、と責めつけた。悪魔は長官の警告におとなしくしたがいなさいとすすめに来たのです、と白状した。

聖マルガレタ
マルガレタ15歳最強伝説(笑)。
ちなみにあのオルレアンのジャンヌ・ダルクの夢に出て、お告げをした三人のひとりがこのマルガレタです。あとは聖女カトリーヌと大天使ミカエル。下の絵で、翼のあるのがミカエルですから、うーむ、どっちがマルガレタだ?と、思ったら左も翼が…あれ?

後ろの…誰かがマルガレタ
悪魔が小物過ぎますが、これも重要なポイントです。キリスト教の強弱というのはこれまでに見てきたよその在り方とは違う。「強い敵をうち負かす→より強い」の英雄のコードを持たない。相手にその力を増幅させる余地がないと力が振るえないのです。悪魔の場合は「付け入る隙」ですが、これは逆のイエスの起こす奇蹟の力も同じです。『福音書』というのはそのほとんどがイエスの起こした奇蹟の技を紹介するものなのですが、死者をも生きかえらせたイエスが唯一奇蹟を「起こせなかった」地があった。他ならぬイエスの育った地、ナザレです。
(イエスが郷里のナザレの礼拝堂で教え始めると)大勢の人がそれを聞いて、驚いて言った、「この人はこんなことをどこから覚えてきたのだろう。この人が授かったこの知恵はなんだろう。また、その手で行われるかずかずのこんな奇蹟はいったいどうしたのだろう。これはあの大工ではないか。マリヤの息子で、ヤコブとヨセとシモンとの兄弟ではないか。女兄弟たちは、ここで、わたし達の所に住んでいるではないか。」こうして人々はイエスにつまずいた。そのため彼の言葉に耳を傾ける者がなかった。イエスは彼らに言われた、「預言者が尊敬されないのは、その郷里と親族と家族のところだけである。」郷里の人々の不信仰のゆえに、そこでは何一つ奇蹟を行うことが出来ず、ただわずかの病人に手をのせて、なおされただけであった。イエスは人々の不信仰に驚かれた。
−−−−−−マルコ福音書

ナザレの古い家屋
先のゲオルギウスの際もそうですが、怖れる心のあった町の人々を前にしてはドラゴンは強大な力を振るうことができた。しかし、その隙のないゲオルギウスの前では「子犬のように」おとなしくなってしまったのでした。マルガレタの悪魔=ドラゴンも同じです。ですので、キリスト教においては「うち負かす」の意味がそもそも違うのです。この辺「キリスト教は悪魔の竜をうち負かして膝下にしくことで……云々」という見解はそもそも見当外れと思われます。
さて、マルガレタの悪魔=ドラゴンですが、まず注意点としては「人の姿に身をやつして」のところですね。続いてこう言っている。
「あなたがこれまでにしてきたことにみずから満足して、もうわたしから離れなさい」と言った。
つまり、これは悪魔がキリストのふりをして出てきた、ということです。後にも見ますが、悪魔というのは偽救世主の姿で現れるものなのです。ま、あっさり見破られてぶん投げられてますが、続いてこの悪魔がなにしに出てきたのか自ら白状してる。曰く、長官の警告に従わせようとしたのだと言う。これはどういったことか。
異教の神へ誘うというのはどういうことなのか。長官に身を任せて貞操を失うことが何を意味するのか(これが「竜に呑まれる」)。それは仮にもイエスの対抗者の位置にいる悪魔自らが出るほどの幕なのか。
出るほどの幕なのです。
これは単に倫理的な「身持ちの堅さ」といった次元で語られる処女性ではないのです。それでは聖母マリアのコードは通らない。では何か。
端的に言いますと、キリスト教の処女性というのは「王を生まないこと」だと思います。次々項の「聖母マリア」で詳述しますが、キリスト教は大地母神の持っていた「産出」のコードを意図的に封じている。それは「生まれる」「死ぬ」の位相を完全にシフトしてしまうことによるのですが、処女性というのは「そこ」に関わるのです。
このような乙女達に囁きかけるドラゴン・悪魔は「操を持ち崩せ、淫乱であれ」という下世話な働きかけをするためにはるばる地の底からやってきているのではありません。彼らは「王を生み、育てよ」と言っている。それはまったくの所これまでに見てきた「蛇の知恵」にほかなりません。彼らは太古とただ変わらぬことをやっている。キリスト教がそれを悪と名付けただけです。
本当かよ、と言いたくもなりますが、続く他ならぬ『福音書』の詳細の検討でそのコードを浮かび上がらせていきましょう。
かつてヘブライの預言者達は警告しました。王を怪物化させてはならないと。
そう、彼はそのヘブライの思想の集大成。イエスとは蛇の産出によって生まれず、蛇の知恵によって育たない、「怪物化しない王」その人に他ならないのです。
『福音書』
先に簡単に述べましたが、『福音書』に関してもう少し詳しくその成立などを述べておきます。「マルコ」「マタイ」「ルカ」「ヨハネ」の四篇によってなる『福音書』ですが、これが特別視されるのはこれらがイエスのあまり長くはない実動期間に居合わせた直接の弟子(十二使徒)の見聞を生の形で伝えていると考えられているからです。
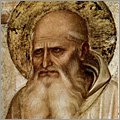 「マルコ」福音書の著者とされるのは、十二使徒のパウロの共働者で、ペテロの通訳だったとされる人。イエスから見ると孫弟子になるでしょうか。イエスの生存中にすでに信者だったバルバナの子ということで、子供のころイエス一行と行動を共にしていたかもしれない人です。(十字架の記述で裸で逃げ出した若者がマルコだという説もあるとのこと)。
「マルコ」福音書の著者とされるのは、十二使徒のパウロの共働者で、ペテロの通訳だったとされる人。イエスから見ると孫弟子になるでしょうか。イエスの生存中にすでに信者だったバルバナの子ということで、子供のころイエス一行と行動を共にしていたかもしれない人です。(十字架の記述で裸で逃げ出した若者がマルコだという説もあるとのこと)。
成立はエルサレム陥落(AD70)の直前、AD65-70あたり。ヘブライ人以外に教えを広めるために書かれたので、ユダヤ人の習慣などを比較的詳しく扱っています。
イエスが教えを始めたとことから書かれており、その誕生などは書かれていません。
 「マタイ」福音書の著者とされるのは、十二使途のひとり、もとはローマの徴税役人だったマタイとされますが、あまりに流暢なギリシア語によるので少なくとも誰かの手は入っているだろうと考えられています。
「マタイ」福音書の著者とされるのは、十二使途のひとり、もとはローマの徴税役人だったマタイとされますが、あまりに流暢なギリシア語によるので少なくとも誰かの手は入っているだろうと考えられています。
成立は良く分かっていない様ですが、エルサレム陥落を暗示する文があるので、それ以降AD70-90頃と考えられています。キリスト教に改宗するヘブライ人のために書かれたので、ユダヤ教が伝える預言をイエスが実現した、という強調が多いです。
ちなみにイエスの誕生に際して「東方の三博士」が来た、というお話があるのはこの「マタイ」だけ。
 「ルカ」福音書の著者とされるのはパウロの共働者であったとされる人。イエスの孫弟子にあたります。元医者であったとされ、非常にギリシア語に堪能。あ、聖書というのはギリシア語ベースで書かれているのです。小アジア地方のローマの有力者(テオピロ閣下に奉呈、とある)にむけて書かれたもので、「マルコ」「マタイ」をベースによりまとまった形に編集したものと、という感じが強いでしょうか。成立は「マタイ」以降、一世紀の終わりにはならないだろう、という感じ。
「ルカ」福音書の著者とされるのはパウロの共働者であったとされる人。イエスの孫弟子にあたります。元医者であったとされ、非常にギリシア語に堪能。あ、聖書というのはギリシア語ベースで書かれているのです。小アジア地方のローマの有力者(テオピロ閣下に奉呈、とある)にむけて書かれたもので、「マルコ」「マタイ」をベースによりまとまった形に編集したものと、という感じが強いでしょうか。成立は「マタイ」以降、一世紀の終わりにはならないだろう、という感じ。
「ギリシア」で見たように小アジアの方は大地母神への依存度が強い地域だったので、ルカは聖母マリアを強く押し出した記述をした、と考えられています。また、実際生前のマリアと親交があったとも。子供のころのイエスや、洗礼者ヨハネの生誕の秘密などが書かれているのはこれだけ。
 「ヨハネ」福音書の著者とされるのは、十二使途のひとりのヨハネ。ですが、確かに実際見たように書かれている部分が多いものの、逆に神学論的に説明的な記述も多く、下って再構成されている感じです。
「ヨハネ」福音書の著者とされるのは、十二使途のひとりのヨハネ。ですが、確かに実際見たように書かれている部分が多いものの、逆に神学論的に説明的な記述も多く、下って再構成されている感じです。
上の三篇がイエスの記録を残す、という比較的素朴なものであるのに対し、ヨハネはすでに「教典」として編集するのだという意図がある感じでしょうか。
成立は不明。と、言いますか再構成がかけられていると書いたとおり、古い形(使途ヨハネのもの)は古く、教典化した部分はAD100以降(AD130くらいにはあったらしい)。ちなみにこの時代のヘブライは(今もですが)同じような名前ばかりで混乱しがちですが、洗礼者ヨハネと使途ヨハネは別人。上に見た再構成をかけたのではないかと言われる「長老ヨハネ」も別人。さらに『ヨハネの黙示録』のヨハネは、使途ヨハネだと一応されますが、また別人であるという向きもあります。。
こういった四篇から成る『福音書』です。特に「マルコ」「マタイ」「ルカ」は共通部分が多く、その順に参照しながら書かれていったと考えられ、また、「マタイ」と「ルカ」に共通するイエスの言行録があまりにも一致するために、共に参照した現存しない「イエス言行録」とでも言うべき記録があったのだろうと考えられています(これをQ資料と言う)。
なんで、こんな詳細を述べているのかといいますと、これはもうこれまでの「神話・伝説」とは違うのだ、ということです。神話・伝説はある土地の数百年数千年の長い世代間の世界観というものを「こんな感じに捉えていた」と示すのですが、キリスト教の時代にはもうそうではなく(無論そう捉えられる部分も少なくないですが)、特定の「誰か」の考えが記されているのだ、ということです。
では、その辺りをふまえて『福音書』を読み解いていくことにしましょう。
わたしの国
ユダヤ教に対する反逆者として捕えられ、ローマからの総督と問答をするイエスは、そこで端的に自らの立場を表明しています。
イエスが答えられた、「わたしの国はこの世のものではない。もしわたしの国がこの世のものであったら、わたしの手下の者たちが、わたしをユダヤ人に渡すまいとして闘ったはずである。しかし実際のところ、わたしの国はこの世のものではない。」そこでピラトが言った、「では、やっぱりお前は王ではないか。」イエスが答えられた、「王だと言われるなら、御意見にまかせる。わたしは真理について証明するために生まれ、またそのためにこの世に来たのである。真理から出た者はだれでも、わたしの声に耳をかたむける。」ピラトがたずねる、「真理とは何か。」
−−−−−−ヨハネ福音書
イエスはこれに答えず、その後ゴルゴダの十字架にかけられることになるのですが、つまり、それが真理を示す、ということでしょう。なんで十字架にかけられるのが真理なのかというのも難しいところですが、実際その後の世界で王冠を戴く王のイメージよりも十字架にかけられたイエスのイメージの方がより広く敷衍したことを考えたらよいでしょうか。
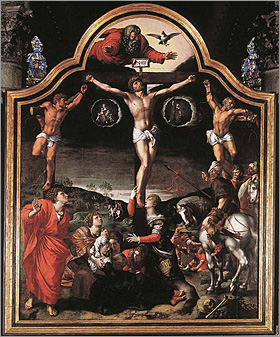
十字架にかけられるイエス
つまりこれは「フォーマット」の問題なのです。イエスが言っているのは自分は「王のフォーマットによる世界の王」ではなく「神の国のフォーマットによる、(そう言いたければ)王だ」ということです。宗教的には「神の国」が「どこか」にあって、それが輝かしい光とともに、この世にやってくるのだ、という「表現」をされるわけですが、そういったイメージは皆お釈迦様的に言うなら「方便」です。
イエスはここで、自分は(正確には神は)新しいフォーマットで世界をリフォーマットする、と言っているわけです。王のコードにより、強い者が勝ち上がりその地を統べることになるのが、新石器革命からローマに至る「王のフォーマット」の世界ですね。イエスはそれを解体する。
これはイエスの教えの道すがらの態度にも良く表れています。イエスはその奇蹟の技で多くの病人を治すのですが、そのこと(イエスが治したと言うこと)は言うな、とたびたび釘を刺す。
イエスが山を下りてこられると、多くの群衆がついてきた。すると一人の癩病人が近寄ってきて、しきりに願って言った、「主よ、清めてください。お心さえあれば、お清めになれるのだから。」イエスは手をのばしてその人にさわり、「よろしい、清まれ」と言われると、たちまち癩病が清まった。イエスはその人に言われる、「だれにも言わないように気をつけよ。ただ全快したことを世間に証明するため、エルサレムの宮に行って体を "祭司に見せ。" モーセが命じた供え物を捧げよ。」
−−−−−−マタイ福音書
イエスが奇蹟の技をやったのは、自らの力の表明ではない。イエスの話を聞き、信仰が生まれたら、その信仰を拡張してみせる(これが奇蹟)。そういった流れなのです。だから、イエスを「試すため」の奇蹟の依頼というのは次のようになる。
するとパリサイ人とサドカイ人とが来て、イエスを試そうとして、神の子である証拠に天からの不思議な徴を示すようにと頼んだ。彼らに答えられた、「あなた達は夕方には『あすは天気だ、空が焼けているから』と言い、また朝早く、『きょうは荒だ、空が曇って焼けているから』と言う。あなた達は空の模様を見分けることを知っていながら、時のせまった徴を見分けることが出来ないのか。この悪い、神を忘れた時代の人は、徴をほしがる。しかしこの人たちには、ヨナの徴以外の徴は与えられない。」イエスは彼らをすてて立ち去られた。
−−−−−−マタイ福音書
奇蹟の技、というのもとどのつまりは「新しいフォーマット」に準じたら、「古いフォーマット」とは違った世界が見えるよ、ということを示すための方便ですね。あくまでも人々が「古いフォーマット(王のフォーマット)」しかないと思い込んでいる凝り固まった頭をほぐすためにある、ということです。
ですので、それが「イエスの力だ」となってはいけないわけです。イエスは王よりも「優れて強い」から、王よりもイエスに頼ろう、ではダメなのです。それでは単に「王のフォーマット」によって既存の王の上にイエスが立つだけのことになってしまう。だからイエスはイエスによって病が治った、とは言うなと再三釘を刺すのです。あくまでその奇蹟は「新しいフォーマット」の見せる一例でないといけない。「王のフォーマット」の「強力さ」の発現であってはならないのです。
王
 ここで、少し「王」と「対称性」について整理しておきましょう。
ここで、少し「王」と「対称性」について整理しておきましょう。
旧石器時代の狩猟生活で、人々は自然の神を戴くことで、人がその力によって崩す自然との均衡(対称性)を回復しようとしてました。これがアニミズムとして多神教のベースとなります。
やがて新石器革命が起こり、人は自然に対して圧倒的な非対称性の力を得てしまう。人間と自然とはバランスを取り合うものでなく、一方的な人間のコントロール下に置かれるものになってしまったわけです。ここに定住と、その都市を統べる「王」が生まれる。
 人々は旧来の対称性の知恵を改変し、自然の神を仮想的に合成させ、ハイブリッドな神の姿を作り、これを王と対置させることにより自然と人間との対称性を計ろうとしました。これが怪物的な自然の神と、それと対称性を持ったことを示す自然の神と融合した王の姿の発生でした。
人々は旧来の対称性の知恵を改変し、自然の神を仮想的に合成させ、ハイブリッドな神の姿を作り、これを王と対置させることにより自然と人間との対称性を計ろうとしました。これが怪物的な自然の神と、それと対称性を持ったことを示す自然の神と融合した王の姿の発生でした。
またこの「自然」の背後、その由来とは、「こっちの世界」と並行にある「あっちの世界」とも考えられました。今で言う「死後の世界」というよりも、生命はこちらで死ぬとあちらで生まれ、あちらで死ぬとこちらで生まれる、といったように「生命エネルギー」のようなイメージが循環するモデルと考えられた。日本ではその「あっちの世界」がミシャグチ空間として示され、エジプトでは太陽神ラーの日没から次の日の出までの「冥界行」として示され、それはまた「大地母神」の統べる地であることを見てきました。
この「こちら」と「あちら」は通常の生命は死んだ時と、生まれる時にのみ行き来するのですが、ここを生きたまま、その姿のまま往来できると考えられたのが「蛇」でした。これは蛇の脱皮の様子が非常に印象的であるため、蛇なら「そこ」を通過しても脱皮して大丈夫なんだと世界的に考えられたためです。
 だから、「蛇」は「こちら」にはない「あちら」からやってくる、より生命力に満ちた「知恵」を語るものだとされ、人々はその「蛇の知恵」を探るべく蛇巫女となり仕え、竜蛇としてこれを祀ったのでした。
だから、「蛇」は「こちら」にはない「あちら」からやってくる、より生命力に満ちた「知恵」を語るものだとされ、人々はその「蛇の知恵」を探るべく蛇巫女となり仕え、竜蛇としてこれを祀ったのでした。
そして、上に見た「王」が自然との対称性を計るための知恵もまた、この蛇がもたらすと、少なくともエジプトやギリシアでは考えられたのです。エジプトでは蛇の女神が王を守り、ギリシアでは蛇巫女が王に託宣を与えました。「あちらとこちらを結ぶ」蛇の知恵を得たならば、その者は自在に自然との対称性を結べる、それが「王の由来」なのです。
 しかし、これに疑問を呈したのがヘブライの民でした。そもそもその「ハイブリッドな自然の神」とやらが勝手な人の仮想です。だったら、「王」は何か非対称な大きな力を振るうたび、勝手に「ハイブリッドな神」を作って祀り、対称性が保たれた「ことにしてまえば良い」、となるのではないか。多神教とはそういうシステムではないのか。そうならば、王はひたすら歯止めのかからぬ「怪物化」をしていくことになるのではないか。
しかし、これに疑問を呈したのがヘブライの民でした。そもそもその「ハイブリッドな自然の神」とやらが勝手な人の仮想です。だったら、「王」は何か非対称な大きな力を振るうたび、勝手に「ハイブリッドな神」を作って祀り、対称性が保たれた「ことにしてまえば良い」、となるのではないか。多神教とはそういうシステムではないのか。そうならば、王はひたすら歯止めのかからぬ「怪物化」をしていくことになるのではないか。
これを糾弾し、ヘブライの民はドラゴンを悪と見立てて神に討たせたのでした。つまり、旧石器時代の大地母神に由来する「多くが生まれ出る」コードに、圧倒的な非対称性の力・技術を振う「王」が接触すると怪物化してしまう、ということです。実際、古代オリエントは歯止めのかからぬ帝国の膨張という現象がバビロンから、ペルシアから、マケドニアから、ローマからと次々起こり、幕を閉じることになります。
イエスは、あるいは「イエスを生み出した人々は」、この一連の流れを「王のフォーマット」としたのです。そして、その危険と限界をふまえ、まったく異なる理により人々の世界をリフォーマットしようと考えた。
だから、悪魔=蛇はイエスをこう誘ったのです。
悪魔の誘い
悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れてゆき、世界中の国々と、栄華とを見せて言った、「あれを皆あげよう、もしひれ伏してわたしをおがむなら。」そこでイエスは言われる、「引っ込んでろ、悪魔! 聖書に "あなたの神なる主をおがめ、" "主に" のみ "奉仕せよ" と書いてあるのだ。」そこで悪魔が離れると、たちまち天使たちが来てイエスに仕えた。
−−−−−−マタイ福音書
これはイエスがまだ教えを始める前、荒野で四十日四十夜の断食の行をしていた最後に悪魔が出てきて言ったことですね。悪魔はイエスに「王にしてやる」と言っている。

悪魔の誘い
そうであってはならない、ということは繰り返し説かれまして、弟子たちも良く怒られる。弟子のヤコブとヨハネが来るべきイエスの栄光の日には自分たちを左右に座らせて下さいとイエスにお願いするのですが、怒られます。
「いかにも、あなた達はわたしが飲む杯を飲み、わたしが受ける洗礼を受けるにちがいない。しかし、わたしの右と左の席は、わたしが与えるのではなく、あらかじめ神に定められた人々に与えられるのである。」ほかの十人の弟子はこれを聞いて、ヤコブとヨハネとのことを憤慨し始めた。イエスは彼らを呼び寄せて言われる、「あなた達が知っているように、世間ではいわゆる主権者が人民を支配し、またいわゆるえらい人が権力をふるうのである。しかしあなた達の間では、そうであってはならない。あなたたちの間では、えらくなりたい者は召使いになれ。一番上になりたい者は皆の奴隷になれ。人の子わたしが来たのも仕えさせるためではない。仕えるため、多くの人のあがない金としてその命を与えるためである。」
−−−−−−マルコ福音書
これが単に「偉ぶるな」「慎ましくせよ」というお説教かというと、ちょっとそうは思えません。端的に「王のフォーマット」でものを考えるな、と言っていると思います。
弟子の間の序列なんて些細なことと言えば些細なことですが、その些細なヒエラルキーだって上と下を生み、非対称の構造を生むのです。非対称の構造が生まれれば、そこに対称性を回復させようとする「蛇の知恵」は働く。
一体に、このような序列に人が納得する理由というのはなんでしょう。誰かが上に立つのは、その人には「権威がある」からだ、と納得するのです。あるいはより「権威にそっている」からだ、と納得するのです。非対称性をそのまま了承しているのではないのです。そうであってしかるべき理由を作り出し、それを了承する。すなわち対称性を回復する蛇の知恵を通して了承する。では、この場合の「権威」とは誰か。もちろんイエスです。他の弟子がこの序列を了承するということは、蛇の知恵を通してイエスを権威とし、それを根拠に対称性の回復を仮想し、了承するのです。つまり、イエスが王化してしまう。
この様に「王のフォーマット」というのは、あるいは「蛇の知恵」というのは、ほんの些細なことにも内在され、人々の世界認識はこれによってなっている。だからイエスはこう言うのです。
しかしわたしはあなた達に言う、いっさい誓ってはならない。神の御名はもちろん、"天" にかけても誓ってはならない。天は "神の御座である" から。"大地" にかけても。大地は "神の足台である" から。エルサレムにかけても。エルサレムは "大王なる神の都" であるから。自分の頭にかけても誓ってはならない。頭は神のもので、あなたは髪の毛一本を、白くも黒くも出来ないのであるから。あなた達はただはっきり『はい』とか、『いいえ』とだけ言え。これ以上は悪魔が言わせるのである。
−−−−−−マタイ福音書
このことにより、イエスの教えが単なる反権力というような次元のものではないことも分かります。この世の人間一人一人の当たり前に持っている認識の実際にまでかかわるのが彼のリフォーマットの目指すものなのですね。イエスはその原理を端的に「愛」と言ったのです。これはロマンティックなことを言っているのではなく、「王のフォーマット」による世界認識の根本を改めよ、というかなりシビアでテクニカルなことを言っている。
神を愛しなさい、隣人を愛しなさい、敵をも愛しなさいと『福音書』は言い、だから『福音書』とは「愛の書」であるとも言われます。しかし、この「愛」がそうそう甘いものではない。
そこにイエスの母と兄弟たちが来て、外に立っていてイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスのまわりに座っていたが、彼に言う、「それ、母上と兄弟姉妹方が、外であなたをたずねておられます。」イエスは「わたしの母、兄弟とは誰のことだ」と答えて、自分のまわりを取りまいて坐っている人々を見まわしながら、言われる、「ここにいるのが、わたしの母、わたしの兄弟だ。神の御心を行う者、それがわたしの兄弟、姉妹、また母である。」
−−−−−−マルコ福音書
イエスの言う愛が、単なる愛情、単なる博愛と違うことが良く分かりますね。彼はやはり愛という言葉で、根本的な世界認識のフォーマットを改めることを説いている。そして、そのリフォーマットが成れば、「この世の支配者(悪魔)がこの世から放り出される(ヨハネ)」。
いずれにしましても、『福音書』に語られているのが愛が栄えれば悪魔は衰える、というだけものであれば、そもそもイエスは迫害される必要もなく、イエスが弟子たちに自分の弟子であることで迫害されるだろうと再三再四予告することもないわけです。それが伝統的なユダヤ教に反するから、というだけならば、「火を地上に投げるために、わたしは来た」とまで言う必要もない。
地上に平和をもたらすためにわたしが来たと思うのか。そうではない、わたしは言う、平和どころか、内輪割れ以外の何ものでもない。今からのち、一軒の家で五人が割れて、三人対二人、二人対三人に割れるからである。父対息子 "息子対父、" 母対娘 "娘対母、" 姑対嫁 "嫁対姑"!
−−−−−−ルカ福音書
悪魔に従わないとイエスははじめにきっぱり退けましたが、その結果はこうなる、ということです。これが『福音書』なのです。これはリフォーマットの宣言であり、それにともなう軋轢と混乱の予告の書です。王を怪物化させる「王のフォーマット」を脱するにはそこからやらなければならない。
だから、イエスもそれが自分一代の説法で成るなどとは考えていませんでした。彼は、彼の生涯とその周辺のコミュニティをひな形として、あるいは「一粒の麦」として歴史に干渉させ、そのリフォーマットの実際を未来に託したのです。
そして、世界認識のリフォーマットとは、究極的には「生と死」の認識のリフォーマトとなります。そのためにはイエス自身の生と死をもって、その意味付けを改変する必要があった。彼は「王のフォーマット」では生まれないし、死なない。
だから、母マリアは処女で彼を懐妊する「必要」があったのです。
聖母マリア
マリアは大地母神か
 実際のところ、処女が子を産み、その子が神のごとくである、というのはマリアに始まるイメージではありません。結構女神は「独力」で子を生み出してる場面が多い。ギリシアでは大地ゲーから単独で生まれた子を「大地から生まれた」と表現していましたね。ゲーは処女神ではありませんが、メソポタミアからレヴァントに連なる地域で、子の神を成しているにもかかわらず「処女」の肩書きでずっと呼ばれる女神は多い。もともとそういったイメージはあったのです。ギリシアのアテーナーも処女神ですが、エリクトニオスを育てた経緯は母であると言っても良い状況を描いています。
実際のところ、処女が子を産み、その子が神のごとくである、というのはマリアに始まるイメージではありません。結構女神は「独力」で子を生み出してる場面が多い。ギリシアでは大地ゲーから単独で生まれた子を「大地から生まれた」と表現していましたね。ゲーは処女神ではありませんが、メソポタミアからレヴァントに連なる地域で、子の神を成しているにもかかわらず「処女」の肩書きでずっと呼ばれる女神は多い。もともとそういったイメージはあったのです。ギリシアのアテーナーも処女神ですが、エリクトニオスを育てた経緯は母であると言っても良い状況を描いています。
大地母神は旧石器時代の狩猟文化から、新石器革命後の初期農耕文化において、大地の実りの多いことを願って祀られた女神ですが、そこに処女女神のイメージが重なるケースはそれなりにあった。そして、上にも述べたようにイエスの母マリアを強調したのは、大地母神信仰の根強い小アジア地域へイエスの軌跡を布教するため、その地へ派遣されたルカでした。
また、確かに続く時代に形成される「マリア信仰」というのは、「拝むもの(偶像)」が否定されているキリスト教を多神教的なコスモロジーに住むヨーロッパの人々(ゲルマン・ケルト)へ布教する際の強力なツールとなりました。彼らがマリアを母なる神のニッチに据えて拝んだのは確かです。より具体的に旧来の大地母神と集合した「黒いマリア像」などが祀られているのが有名ですね。

黒い聖母子像
しかし、イエスがそう考えたのかと言うと疑問です。というか、おそらくイエスはマリアに関して何も言及していない。言及していないどころか「母」を斬って捨てているところがあるのは前項に見た通り。従来の大地母神のニッチを自身の教えの重要事だとイエスが思っていたのなら、それは語られているはずでしょう。
では、マリア信仰というのはイエスと離れた後世の信者の産物なのかと言いますと、話はそう簡単でもありません。後に見るように、大地母神を代替する、というのは間違いなくイエスの思惑の真逆だと思われますが、処女にしてイエスを孕んだ、というのはイエス自身の思想から出てもおかしくないのです。それはどういうことか。
イエスはマリアには言及していませんが、「父」に関してはそれが主なる神であり、「お父様」であり、自分が「神の子」であることを繰り返し口にしています。つまり肉親としての「父」というのははじめからパージされている。で、あるならばイエスの時点で少なくともイエス(自分)は神とマリアの子である、という認識は当たり前にあったわけですから、「処女マリア」は、その表現を思いつくかつかないか程度の「時間の問題」だったと言えましょう。
このマリアが何者か。イエス自身の言及がない以上は、マリアに関してはイエスの他の言動との整合性からその本質を探るしかない。それは「家族」とは何かの問題です。
ジーンとミーム
ここでお話を少々ぶっ飛ばしまして、情報のことについて話します。ジーンとミームのことです。ジーンとはゲノム。遺伝子情報のことですね。ミームとは模倣子(と訳されることが多いです)。リチャード・ドーキンスが発案したジーンの対角を成す概念です。
情報学的なことを云々するとまたエラいことになるので、ここは例で簡単に紹介しましょう。
親が子を産んだら、子は親のジーンを半分ずつ継いだ遺伝情報体であることになります。この血縁による生物としての情報の伝達がジーンによる情報の継承構造です。これは単に「生物」数世代のスパンで見るものではなく、そもそも情報は「無機物→(鉱物?)→有機物(RNA→DNA)→植物→動物」と、徐々に情報体の総体が大きく、また個体に、より多くの情報が「折り畳まれるように」発展して来た、とも言えます。
一方ミームとはジーンによらない情報の伝達全般を指しますが、狭義では、記号化された情報を運用処理する「ヒトの脳」の行う文化行為に継承される意味の素子を指します。例えば、ソクラテスの弟子がプラトンで、その思想「ミーム」は継承されますが、彼らは肉親ではないのでジーンの継承は関係がない。
さらに、これは単に記号体系の継承という話に止まりません。「ミーム(模倣子)」と訳される通り、ミームはそれが存在することで、その存在を継承するキャリアを引き寄せる性質があります。世に大きなインパクトを与えたミームは、まわりに模倣するものを大勢生み出す。ジーンのような生物としての継承のインフラ(DNA)は持ちませんが、文字とメディア(粘土板・紙からコンピュータへ)が発明された時点でかなり物質的根拠も持ったと言えましょう。
一般的に考えるならば、ジーンによる生物としての継承構造の上部にミームによる文化の継承構造が乗っかっている、というイメージになりますね。んが、そうではない場合もある。
例えば大きな仕事を成した学者やアーティストにとっては、「子供」が「その作品」を指す場合があります。この場合、願われるのは自分のジーンとしての子供の存在ではなく、ミームとしての「子供」が自分の死後も継承されていくことです。つまり、肉親ではない「弟子」が自分のミームを継承することの方が血を分けた子の育成・ジーンの継承に優先してしまう場合があるということです。
そして、そうであるならば、ジーンとミームの優先順位を逆転させることを前提とした思想が生まれても別段おかしくはない(妥当性の話じゃないですよ?)
端的に言いましょう。
それがイエスの思想です。
霊のコミュニティ
実にイエスとは「ミーム原理主義」とでも言うべき人です。神の子であるとか神の国であるとか霊であるとか精霊であるとか、表現は当時の記号によってますが、そこで「いやいやいや」とならずに読み替えてみれば明らかです。彼は言います。
(パリサイ人のニコデモが言った)「先生、わたし達はあなたが神のところから来られた先生であることを知っています。神がご一しょでなければ、あなたのされるあんな徴(奇蹟)はだれもすることはできません。」イエスが答えて言われた、「アーメン、アーメン、わたしは言う、徴を見て信じたのではいけない。人は新しく生まれなおさなければ、神の国にはいることはできない。」ニコデモがイエスに言う、「このように年を取った者が、どうして生まれなおすことが出来ましょう。まさかもう一度母の胎内に入って、生まれなおすわけにゆかないではありませんか。」イエスは答えられた「アーメン、アーメン、わたしは言う、人は霊によって生まれなければ、神の国に入ることは出来ない。肉によって生まれたものは肉であり、霊によって生まれたものだけが霊であるから。『あなた達は新しく生まれなおさねばならない』と言ったからとて、すこしも不思議がることはない。風(プニューマ)は心のままに吹く。その音は聞こえるが、どこから来てどこに行くか、あなたは知らない。霊(プニューマ)によって生まれる者も皆、そのとおりである。」
−−−−−−ヨハネ福音書
神の国に至る信仰が、イエスの考える「新しいフォーマット」であり、それを身につけ、その見方で世界を見るようになることを「生まれなおす」「霊によって生まれる」と言っています。おそらく、その「生まれなおす」イメージが有名な『キリストの変容』でしょう。イエスは生まれなおす必要はないのですが、そのイメージを伝えた、ということです。

キリストの変容(上部)
そのタイミングは生物としての母から生まれることとは「何ら関係がない」。「生まれる」のポイントが大分違ってきているのがお分かりでしょう。もっと端的に「生きている」こと自体が一般の動物としての生命活動とかけ離れたところにシフトしていることを示す言葉もあります。
死人が復活することについては、聖書にはっきり書いてある。モーセの書の茨の薮の燃える話のところで、神がモーセにこう言われたのを読んだことがないのか、−−"わたしはアブラハムの神、またイサクの神、またヤコブの神である" と。ところで神は死人の神ではなく、生きている者の神である。だからアブラハム、イサクなども皆復活して、今生きているわけではないか。あなた達は大間違いをしている。
−−−−−−マルコ福音書
これは端的にミームとしての継承がある状態を「生きている」と表現しているのだ、と取っても良いでしょう。というかほかに捉え様がない。
直接肉親との関係と生死を示すものとしては、
またほかの一人の弟子が言った、「主よ、お供をするその前に、父の葬式をしに行かせてください。」イエスはその人に言われる、「今すぐわたしについて来なさい。死んだ者の葬式は、死んだ者にまかせよ。」
−−−−−−マタイ福音書
ヒデエ話の様ですが、イエスによるフォーマットではそうなるのが当然であるのはここまで読んできたらお分かりでしょう。また、上に言う「霊」が死後の霊魂がどうこう言う問題でないこともこれで良く分かりますね。煎じ詰めれば次のような言葉になるのです。
大勢の群衆がイエスと一しょに旅行をしていると、振り向いて言われた、「わたしのところに来て、その父と母と妻と子と兄弟と姉妹と、なおその上に、自分の命までも憎まない者は、だれもわたしの弟子になることは出来ない。自分の十字架を負ってわたしについて来ない者は、わたしの弟子になることは出来ない。
−−−−−−ルカ福音書
葬式どころか、そのような血縁によるコードに自らを位置づけていたのでは「わたしの弟子になることは出来ない」と言っています。
つまり、イエスは血縁によるジーンを継承するためのコミュニティを解体して、ミームを継承するコミュニティによって社会の基盤を再構成すべきだと言っているのです。ラディカルなんてもんじゃありません。事実、現在に至るもそのような変革が恒久的に成された社会はない。
これがイエスによるところの「新しい家族像」であるからには、マリアの本質というのも明らかです。人は母から生まれた後、イエスの言に触れて「生まれなおす」ので良い。しかし、その「イエス」ははじめから霊そのものでなければならない。ジーンのコードから解放されていなければならない。途中から見方を変えたという存在では「神の子」足り得ない。だから、イエスは肉としての母がいてはならない。マリアとはイエスがはじめから肉のコード(ジーンのキャリアであること)を持たない存在であることを証明する者でなければならなかったのです。ここからマリアの処女懐妊伝説は生まれたのですね。

受胎告知
マリアは大地母神ではない。それどころか大地母神の保証するジーンの継承構造を解体する象徴としてその伝説は生まれたのです。
処女と悪魔
これが、前々項のマルガレタのところで指摘したキリスト教における処女性の重視の深層です。それは貞操の問題ではない(色々階層がありますから「ではない」ということはないですが)。悪魔は単純に「子供を産め」と言っているだけです。なぜならば、悪魔は蛇であり、大地母神のお使いであり、ジーンのコードでその生物としての人の継続と繁栄を保証する役目を持った存在だからです。
しかし、イエスにおいてはそのジーンとしての出自を自らの出自と確定した時点で「王のコード」の因子を宿してしまう。王のコードもまた「蛇の知恵」だからです。ゆえに、王のコードから逃れ、王のフォーマットをリフォーマットしてゆくには、ジーンのコードから逃れ、ミームのコードによって成り立つコミュニティが形成される必要がある、とイエスは(あるいはイエスに連なるヘブライの知恵は)考えたのです。
だから、イエスの母のマリアは蛇の知恵から逃れた母でなければならなかった。あるいはイエスを生み出すコミュニティがそうでなければならなかった。ルカの福音書によれば、洗礼者ヨハネの母エリザペツもまた大天使ガブリエルの降臨によりヨハネを身籠っています。そしてまた、下ってはイエスの母マリアもまた、その母アンナの天使の降臨による懐妊で誕生したという伝説を持ちます。
アンナの懐妊はまた「無原罪の宿り」とも言われます。原罪とは何か。それは「オリエント2」で見た、蛇の知恵を宿したアダムの妻の姿にほかなりません。「無原罪の宿り」とは「蛇の知恵から逃れた懐妊」のことなのです。イエスを生み出す環境そのものが蛇の知恵から逃れていなければならなかった。「無原罪の宿り」とはそういうことです。

無原罪の宿り
ここにおいて、キリスト教の女性像は二分することになります。すなわち、蛇の知恵から逃れた処女の母、ミームの系譜を継承するマリア。そして、大地母神に連なる蛇の知恵で王の因子を持つ子を産む母、ジーンの系譜を継承する「女」。後者にはこれまでの一切の女神のイメージが放り込まれ「悪魔」となります。女性像が一方でマリアに、もう一方で悪魔になるのはこういったことなのですね。
そうは言ったものの、ここを「悪魔」とするとそれに捕えられることが「罪」となり、抵抗があるでしょうが、これを太古からの大地母神の知恵「蛇の知恵」だと思えば、逆にそこから脱することは不可能事と言って良いほど難しい。実際、キリストの教団内にはジーンのコードを脱したコミュニティが生まれ、受け継がれましたが、それが一般に敷衍することなどなかった。
この方(言葉・ロゴス)は、この世にうまれて来るすべての人を照らすべきまことの光であった。この世にきておられ、世はこの方によって出来たのに、世はこの方を認めなかった。いわば自分の家に来られたのに、家の者が受けいれなかったのである。しかし受けいれた人々、すなわち、その名を(神の子であることを)信じた人には一人のこらず、神の子となる資格をお授けになった。この人たちは、人間の血や、肉の欲望や、男の欲望によらず、神の力によって生まれたのである。
−−−−−−ヨハネ福音書
と書いたヨハネ自身がマリアの処女懐妊の記述をしませんでした。ヨハネが処女懐妊という「有り得ない」ことを記述しなかった、という見方では何故上のように書いたのか不明となります。問題は処女懐妊があり得るかどうかなんてことではないのです。
ジーンのコードによる社会の基盤、「血族による家族」をミームのコードによる基盤に差し替えられるか否か。現状、全面的にそれを行うのは難しい、ヨハネはそう言ったのです。
さて、以上がマリアの処女懐妊伝説に見る、イエスが敷衍しようとした「神のフォーマット」が示す「生の認識」のシフトでした。彼は「生まれる」ことがどういうことか、それを肉親の母から生まれるポイントではなく、「神のフォーマット」によって(霊によって)「生まれなおした」ポイントに置いたのです。ジーンのコードからミームのコードへシフトすることを説いたのです。
そして、自分自身の誕生が、肉の誕生と無縁であることを主張して、自らが「王の因子」を持たない神の子であることを表現したのでした。しかしこれは生死の一端です。彼は同様に自身の「死」によって、「生」同様のコードのシフトを「死」の認識の上に示さなければならなかった。
十字架にかけられるイエスの死と復活。ここにおいてわれわれは、彼の生涯が完全に一定のコードによってコントロールされている物語であることを理解するでしょう。それはまた、そのコードを書いたのが誰だったのか、というお話でもあります。
イエス・キリスト
永遠の命
イエスは自身の生まれには言及しなかったのに対して、自身の死に関しては繰り返し発言しています。つまり、生の在り方より死の在り方をどう考えたかの方が端的に表明されていると言えましょう。ちょっと長いですが、以下のあたりが良いでしょうか。
あなた達は皆別れを悲しんでいるが、本当にわたしを愛するなら、わたしの掟を守り互いに愛しなさい。そうすればわたしも父上に願って、わたしに代わるほかの弁護者(パラクレートス)をおくっていただき、いつまでもあなたたちと一しょにおるようにしてあげる。これは真理の霊である。この世の人には見えもせず、わかりもしないからこれを受けいれることが出来ない。しかしあなた達にはこの霊がわかるいつもあなた達のところをはなれず、また、あなた達のところにおるのだから。
わたしは父上の所に行くけれども、あなた達を孤児にはしておかない。すぐかえって来る。もう少しするとこの世の人はもはやわたしを見ることができなくなるが、あなた達は間もなくわたしを見ることができる。わたしは死んでもまた生き、それによってあなた達も生きるからである。
そのときあなた達は、わたしが父上の中におるように、あなた達がわたしの中に、わたしがあなた達の中におることを知るであろう。わたしの掟をたもち、これを守る者、それがわたしを愛する者である。わたしを愛する者はわたしの父上に愛され、わたしもその人を愛して、その人に自分を現わすであろう。だからわたしを愛する者だけが、わたしを見ることができるのだ。
−−−−−−ヨハネ福音書
「愛する」がどのような内容を示すかは先に述べた通り。共通コードを持った者には、そのミームが継承され「見ることができる」のだ、と言っています。
「人の記憶にあるかぎり、その人は生き続けているのです」くらいのことは誰でも言いますが、「そのために」十字架にかかるとなりますとわけが違ってきます。「死んでも生き続ける」と言っているのではない。「生き続けるために死ぬのだ」と言っているのです。あるいはそのフォーマットを有効に働かせるために死ぬのだと言っているのです。すでに生物の個体としての「生死」はほとんど意味を失っている。イエスにおいてはそれは後に見るようにプログラムの発動キーの役割になってしまっています。

最後の晩餐
このような死生観のシフトによって、あるいはミームの継承がその「生」である、という生命観へのシフトによって、イエスは「永遠の命」が与えられるのだと言う。このあたりをユダヤ教団の者に対して表明する言はこんな感じ。
だが、あなた達は信じない。わたしの羊ではないからだ。わたしの羊はわたしの声を聞きわける。わたしは彼らを知っており、彼らはわたしについて来る。するとわたしが永遠の命を与え、彼らは永遠に滅びない。また彼らをわたしの手から奪い取る者はない。というのは、彼らをわたしに下さった父上はすべての者より強いので、彼らを父上の手から奪い取ることのできる者はだれもなく、しかもわたしと父上とはひとつであるからだ。
−−−−−−ヨハネ福音書
この「永遠の命」が「今」の延長に「死なない」不老不死をもたらすことを言って「いるのではない」ことは、別のユダヤ教団の人たちへの言から分かります。
するとユダヤ人がイエスに言った、「君はまだ五十にもならないのに、アブラハムに会ったのか。」イエスは言われた、「アーメン、アーメン、わたしは言う。アブラハムが生まれる前から、わたしはいたのだ。」
−−−−−−ヨハネ福音書
アブラハムというのはヘブライの民の祖です。イエスから二千年以上前の人ですね。イエスの言う「永遠の命」が未来方向だけのベクトルを持つものではないことはこれで明らかです。すなわち「存在」の定義が、一定の継承をされているミームへのコミットである、となっているのです。それは今現在の肉体の由来とは関係がない。ここにおいて生物の個体としての死と生を基準に組み立てられる「蛇の知恵」「王のフォーマット」は、完全に無効化することになります。イエスは死地に赴こうとする自分を止めるペテロを叱ります。
(自らの死を公言し始めたイエスに対して)ペテロはイエスをわきへ引っ張っていって、忠告を始めた。救世主(キリスト)が死ぬなどとは考えられなかったのである。イエスは振り返って、弟子達の見ている前でペテロを叱りつけられた、「引っ込んでいろ、悪魔(サタン)!お前は神様のことを考えずに、人間のことを考えている!」
−−−−−−マルコ福音書
なんと、イエスの死を止めるのが悪魔なのです。では当の悪魔はなにしているのか。これは使徒の一人ユダに囁き、イエスをユダヤ教団に売らせていますね。しかし、それはペテロの逆、つまりイエスの計画を遂行するための役割になってしまっている。悪魔はイエスを死の淵へ誘うことによって、イエスの目指す死のシフトの訪れを実現せしめている。
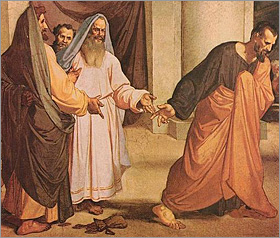
イスカリオテのユダ
「永遠の命」が、蛇の知恵においてその究極の表現であることを「オリエント2」のギルガメシュの所で見ました。王がその覇道の果てに不老不死を目指すのは、単に己の欲望の肥大からではなく「生命の秘密」という「蛇の知恵」の象徴を得ようとするからなのだと述べました。それをイエスは個としての生命現象の延長からパージしてしまったのです。「永遠の命」というまったく同じ表現の内容をミームの継承の次第としてリフォーマットしてしまった。
すでにここでは悪魔はイエスの対遮者ではなくなっています。もう、悪魔の扱う「蛇の知恵・王のコード」は成り立たないし、通らない。だからイエスは宣言をするのです。
これらのことを話したのは、あなた達がわたしにしっかり結びついて、平安を保つことができるためである。この世ではあなた達に苦しみがある。しかし安心していなさい。わたしがすでに世に勝っている。
−−−−−−ヨハネ福音書
この局面、残っているイエスの仕事はエンターキーを押すことだけ。十字架に登ることだけだったのです。
預言の成就
無論、だからといってこの時点でそこまでの勝利を確信させる下地があったのかと言うと疑問です。少なくとも『福音書』に見る使徒達の姿はおぼつかない。ですが、逆にこれで「あがり」なのだとしたらどうなるのか。イエスの勝利宣言を疑わないとしたらその裏付けに何が考えられるのか(実際その後のキリスト教の敷衍を見たらイエスの勝ちなのです)。
『福音書』のそれぞれに共通して後半顕著な事柄に、イエスが自身の死があらかじめ決められたことであり、それは成就されねばならないことなのだと、彼自身が繰り返し口にする、という点があります。それは自身の未来を預言している、ともとれるでしょうが、実際の台詞のニュアンスはちと違う。
この時から、イエスは、「人の子(わたし)は多くの苦しみうけ、長老、大祭司連、聖書学者たちから排斥され、殺され、そして三日の後に復活せねばならない。神はこうお決めになっている」と弟子たちに教え始められた。
−−−−−−マルコ福音書
見よ、わたしはきょうとあしたは、まだここにいて悪鬼を追い出し治療を行い、三日目に仕事が終わって全うされる。とはいえ、きょうもあしたもあさっても、わたしはたえずエルサレムへ向って進みゆかねばならない。予言者がエルサレム以外の所で死ぬことはあり得ないのだから。
−−−−−−ルカ福音書
わたしは胸がどきどきしてならない。ああ、なんと言って祈ったら良いのだろう。『お父様、この試みの時からわたしを救ってください』と祈ろうか。いやいや、わたしはこのため、この時のためにこの世に来たのだ。
−−−−−−ヨハネ福音書
これらはどれも「そういう脚本なのだ」と言っているように読めます。
これは、師が死罪とされピンチに立った初期キリスト教教団が、何とかその死罪と教えとの整合性を保つために、その死が「預言の成就なのだ」と「意味付けを創作」した、とも言われますが、これはどうも上手くない。単純に、そうまでして「キリスト教」を立ち上げなければいけない理由がないのです。その後巨大化し、現在巨大な組織であるから「立ち上がらない」というイメージはわき難いかもですが、イエスと十一人の弟子がそのまま歴史の流れに埋没してしまっておかしい理由というのはない。

ゴルゴダの丘へ向うイエス
大体あの局面、イエスはどうとでも「死なずにすんだ」はずです。『福音書』には当時すでに大きな脅威となっていたように書かれてますが、実際それほどの注目を集める集団だったとは考え難い。事実統治者のローマ側にはイエスに関する記述などほぼ何もないのです。むしろ、後に見るようにキリスト教はイエスの死によってローマの脅威となる程のカードを手に入れているのです。
イエスを追いかけ回した旧来のユダヤ教団との軋轢だとしても、ユダヤ教団の一部が怒ったらイエスはナザレに引きこもればすんだし、よしんばイエスが手にかかっても、弟子達はそこで「お開き」にしても良い程度の集団規模だったと思われます。イエスがつかまった時にはみんな散り散りに逃げ出してますしね。
やはり、あれは上に見たように当初から織り込まれていた「死」なのであると思います。と、言いますか、少なくともこの頁で見たイエスの思想の一貫性というのはそうでないと成り立たない。実はイエスは十字架にかけられる気なんかなかったんだけど、つかまって殺されちゃいました。弟子達はあわてて、その出来事に意味付けする「預言成就」説をでっち上げました、では、イエスの思想はまったく空中分解してしまう。
イエスにはその死までを含めての後見人がいた。それが一番通る筋です。
弟子達はイエスなき後、わずか一世代でローマ各地に強力な組織を作り出す作業に入っている。イエス自身はエルサレムとガリラヤ湖の周辺でミクロな活動をしていただけなのに、それをいきなりローマ帝国相手に広域化させるスキルや後ろ盾がどこから出てきたのか?どうしたって、ここにはギャップがあるのです。
死海文書
その辺りの謎を解く鍵がみんな大好き(笑)『死海文書』です。
ここを読んでおられる方がこの『死海文書』にどんなイメージを持ってるのか分かりませんが…ぶっちゃけ町の本屋さんへ行って『聖書』を買ってきて読むのと『死海文書』を読むのにどれだけ差があるのかと言ったら、ま、ないでしょう(笑)。つまり『死海文書』とは『(旧約)聖書』だと思って遠からずです。もちろん研究者・横好きの人には興味深いのですが、別段その時代のオリエント各地の思想とかけ離れたことが書いてあるわけじゃないということです。

クムランの洞窟(こんなのがいっぱいある)
『死海文書』とは死海の畔、クムランという名の地の洞窟群に納められていたユダヤ教の教典群を指します。『死海文書』という一冊(というか一巻)があるわけじゃないですよ?発見からしばらくヴァチカンがその調査と公開を大変コントロールしたために、とんでもない尾ひれがついて伝説化していましたが、今は全文公開されています。

『死海文書』の巻物のひとつ
クムランにそういう宗教集団が住んでいたのだ、という向きと、エルサレム陥落の際に、宮殿内の「外典」に相当する文書群をエルサレムの神官たちがこの洞窟に隠したのだ、という向きがありますな。いずれにせよそんなわけで『死海文書』は正当なユダヤ教からはやや外れた教典群である、というのは本当です。
その「やや外れた」ユダヤ教徒というのが問題でして、彼らは「エッセネ派」と呼ばれます。エルサレムの主流派の「政治的な」有り様を批判して俗世間を外れるのを良しとした一派とされます。一元論のユダヤ教なのに、この世を「光と闇」の戦いであると強調する教義が特徴でして、まさにそういったことの書かれた文書がクムランから出たわけです。
光の子らの征服は、まず最初に、闇の子らの一団、ベリアルの軍隊、エドムとモアブの集団や、アンモンの子らや(東方と)ペリシテの(大勢の子ら)、神の契約の冒涜者たち、つまりレビの子ら、ユダの子ら、ベニヤミンの子らを援助しに(やってくる)アッシュールのキッティームの集団やその臣民に対して行われる。
砂漠に追放されたものたちが、彼らと戦う。なぜなら、追放された光の子らが諸民族の砂漠から戻り、エルサレムの砂漠で野営するとき、(戦いは)すべての集団に(宣言される)から。
−−−−−−BC2C 戦いの書
てな具合でして、どこのゾロアスター教ですの、という感じ。で、このあたりが黙示録の終末観へ影響を与えてるのを始め、このエッセネ派の表現にはキリスト教の『福音書』に語られるイエスの言動を先取りしているものがあるのですね。それがイエス以前のものとなりますと、つまりイエスは「発案者」でなく「継承者」であることになる。このあたりがヴァチカンが公開を渋っていた理由でして、信者の集団にはそれは大問題でしょうが、門外漢が鵜の目鷹の目でつつき回すような「世界の秘密」が書かれていたりするわけではないのです(大体ユダヤ教がカバラーなどで秘教化するのはもっと後の時代です)。
この「先取りのエッセネ派」ですが、彼らはイエスの当時でも、『福音書』に出てくる「パリサイ人(ファリサイ派)」や「サドカイ人(サドカイ派)」に並ぶ有力な教派でしたが、なぜか『福音書』には一切出てこない。これがなぜかと言うならば、そもそもイエス自身がこの一派だったからだ、というわけです。おそらくは洗礼者ヨハネがこの一派の者で、イエスはその弟子であったのだろうと考えられています。なるほど『死海文書』がイエスの教えを先行して記していることと符合する。
つまりこうです。バビロン捕囚により自らの宗教のしっかりとした確立を目指したヘブライの民でした。捕囚が解け、エルサレムに戻ってきたのがBC6C。その後強国の影響下にありながらもエルサレムを中心にユダヤ教をまとめて行くのですが、BC1Cくらいには中心となる教団が体制化・政治化してしまったため、これを良しとしないエッセネ派などが野で活動をしていた、ということです。
そして彼らの一部は一種の宗教革命を起こそうとした。旧来のユダヤ教をベースとしながら、エルサレムの宮殿中心主義にとらわれずに、(結果として)ヘブライ人以外も救済の対象とするより抽象的な新時代の宗教を立ち上げようとした。
ここで、その旧来のユダヤ教の根拠である「旧約」に対して、これが神との新しい契約(「新約」)で更新された、というストーリーで一新を図るために、キャストされたのがイエスの一行だった。それが、イエスに与えられた脚本「預言」だったのです。
イエス本人は広域に自身の思想を広める必要はなかった。彼の仕事は彼とその直接の関係下にある使徒達とのコミュニティによって、これまでに見てきた「王のフォーマット」をリフォーマットするための新しい人間関係のコアをひな形として記録出来れば良かったのです。そのイエスの生涯とコミュニティの記録をコアカーネルとして、より巨大な歴史へアクセスさせて行くプログラムは別途後に用意されていた。イエスはだからこう言ったのです。
「神の国を何にたとえようか。それはパン種に似ている。女がそれを三サトン(二斗)の粉の中にまぜたところ、ついに全体が発酵した。」
−−−−−−ルカ福音書
アーメン、アーメン、わたしは言う。一粒の麦は、地に落ちて死なねば、いつまでもただの一粒である。しかし死ねば、多くの実を結ぶ。
−−−−−−ヨハネ福音書
イエスの思想にはこのように自分の行動が、「パン種」として大きな流れに接触し、それが発酵手順のような反応を起こして行って最終的に事が成る、と考えていると思わせるものが多くあります。失礼ながら、弟子達にも「あんた達が今スーパーじゃなくても別に良いのだよ」と言ってるように見える。
いずれにしても、イエスには後を託せる後見人、あるいは集団があったと見るのが妥当でしょう。最も脚色の少ないと見られるマルコの福音書は最後にとんでもない謎を描き、いきなりその幕を閉じます。そのラストまでの全文を引用して、この項の最後としましょう。
第十六章 翌日、日が暮れて安息日が終ると、マグダラのマリヤとヤコブの母マリヤとサロメとは、イエスの体(亡骸)に油を塗りに行くために、油にまぜる香料を買いととのえた。そしてあくる朝、すなわち週の初めの日(日曜日)の朝、ごく早く、日が出ると墓場に行く。「誰か墓の入口から石をころがしてくれる者があるだろうか」と互に話しながら、ふと目をあげて見ると、石はもうころがしてあった。彼らが心配したのは石が非常に大きかったからである。墓に入ると、白い衣をきた一人の青年が右手の方に坐っているのを見たので、ぎょっとした。青年は彼らに言う、「驚くには及ばない。あなた達は十字架につけられたナザレ人イエスをさがしているが、もう復活されて、ここにはおられない。そら、ここがお納めした場所だ。さあ行って、弟子たち、とりわけペテロに、『イエスはあなた達より先にガリラヤに行かれる。前にあなた達に言われたとおり、そこでお目にかかれる』と言いなさい。」女たちは墓から逃げ出した。びっくりして震えあがったのである。そしてだれにも何も言わなかった、恐ろしかったので。……
−−−−−−マルコ福音書
黙示録のドラゴン
王のコードの無効化
イエス亡き後、初期のキリスト教団は主に小アジア(ギリシアからトルコ)を中心にその地歩を固めていきます。が、ローマはこれを放ってはおかなかった。おそらく、キリスト教の基本思想に「王のコード」を無効化するものがある、ということはすぐさま認知されたと思います。
これは、遠く離れた日本にキリスト教がやってきた際のことを見ると良く分かりますが、幕府がキリシタンを執拗に弾圧した理由がまさにそうでした。幕府はキリスト教が敷衍した結果などをローマなどの歴史をふまえて知っていたわけではないでしょうが、増え始めたキリシタンを見てすぐさま「まずい」と見抜いています。
そして、そのローマの地に初期キリスト教が広まっていく過程というのがすさまじいものでした。教えを説いたり公共事業を行ったりという普通の布教もそれはありましたが、彼らの切り札というのは「殉教」だったのです。それはまさにこれまでに見た、イエスにより「リフォーマットされた」生と死の概念のシフトによる、「王のコード」の通らない戦い方そのものでした。
この「殉教」が、十字架にかかったイエスがその死をもって続く者達に与えたその思想の結晶なのです。「王のコード」を無効化する戦い方は「負けるが勝ち」を地で行く思想です。

殉教
ローマはキリスト教徒を打ち破ることができなかった。彼ら(ローマ)の持つ「王のコード」で、その「強さ」で、一人の教徒を痛めつけ、殺す。普通ならこれで1勝です。しかし、キリスト教徒はその一人の殺害によって数倍に増えてしまう。
まず「殉教」が「救い」である、という上で見た「生と死の概念のシフト」がもたらしたイエスのコードが、民衆に紹介されます。
で、言葉では半信半疑だった彼ら民衆は、それを説いていた者が、怯むことなくローマの手にかかるのを見て「信じて」しまうのです。そう簡単に信じるものかい、と現代のわれわれは思うのですが、歴史的に見て「この方法」がキリスト教の伝播からすぐさま他地域でも発動する様を見ますと(先の日本もそうです)、実際それは起こったことなんだろうとしか思えませんね。
力を持たない民衆は、「その方法」ならば強者に対抗できてしまう、という一縷の望みを知ったのです。
具体的にその様子を見るならば、この頁最初に出てきた聖女マルガレタその人の行状がまさにそれです。
「ああ、マルガレタ、あなたがずたずたに全身を引き裂かれるのを見ると、ほんとうに気の毒でなりません。神々を信じないばかりに、せっかくの美しさも、すっかり台なしじゃありませんか。このうえ命までなくさないように、いまからでも神々をお信じなさい」しかし、彼女は答えた「あなた方の忠告は、間違っています。どうかもう立ち去ってください。この肉の苦しみは、たましいの救いなのです」それから、こんどは長官にむかって、「あなたは、血に飢えた浅ましいけだものです。そうしてわたしの肉体に暴力をふるっていますが、わたしのたましいは、永久にキリストさまのものですよ」
さらには火あぶりにされた後、火傷の痛みをひどくさせようと水につけられたりするのですが、
ところが、そのとき突然大地が鳴動した。そして、マルガレタは、みんなの眼のまえで傷も負わずに樽から出てきた。この奇跡を見て、五千人の人々が信者になった。これらの人たちは、キリストの皆のためにことごとく首をはねられた。裁判官は、民衆の中からさらに多くの信者が出はせぬかと不安にとりつかれ、ただちにマルガレタの首をはねよと命じた。
こうしてマルガレタは斬首さてしまうのですが、その際の台詞も「さあ、剣をふりあげて、わたしを打ちなさい」です。マルガレタも奇跡を見て信者になった民衆も皆殺されてしまいましたが、それによって信者は増えてゆくのです。
この、従来の「王のコード」がまったく通用しない戦い方をするキリスト教信者たちの増殖に、ローマは恐怖した、と言えるでしょう。最終的に313年のミラノ勅令で公認されるキリスト教ですが、要はローマ側がもう「手を引いた」ということだと思われます。ドラゴンは手の出し様を失ったのです。

ミラノ勅令
しかし、書けば簡単ですが、ぶっちゃけ死んじゃってるわけですし、今のわれわれからは「その戦い方」というのは狂気にしか見えません。「別に王のコードに沿って暮らせば良いのでは?」という疑問、疲労、逆転はすでにその当初から発生していました。だからヨハネはその逆転を予防するためにメッセージを発したのです。時は紀元100年の少し手前。
メッセージの名は「ヨハネの黙示録」と言われます。
ヨハネの黙示録
名前は非常に有名ですね。曰く第七の封印が解かれるのであると、曰くハルマゲドンであると、曰く666の獣であると、曰くバビロンの滅亡であると……が、とりわけこの頁ではその辺りはどうでもよろしい。

黙示を受けるヨハネ
重要なのは、上に見たようにこの書が疲弊する初期キリスト教団の「戦い」へのメッセージである、「王のコード」に戻ることなく「イエスのコード」を貫いて戦え、というメッセージであるという点です。つまりは、「オリエント2」から見てきた「ドラゴンのコード」と「アンチドラゴンのコード」の最終決戦が描かれるのがこの「ヨハネの黙示録」である、ということなのです。では、まずは全体の概要を押さえておきましょう。
序文
冒頭の挨拶
第一部 教会の現在
1予備の幻
2七つの教会への使信
第二部 未来の出来事
1導入的な幻
2七つの封印
(1)六つの封印の解除
(2)幕間劇−信徒の保護
(3)第七の封印の解除
(4)七つのラッパの災い
3神の秘められた摂理の実現
(1)竜の支配
(2)小羊の信従者と獣の信従者
(3)最後の七つの災い
(4)バビロンの滅亡
(5)サタンの支配の終り
(6)神支配の始まり
奨励と結び
エピローグ
これが全体の構造です。以下タイトルや引用は岩波書店『<新約聖書V>パウロの名による書簡・公同書簡・ヨハネの黙示録』によります。
まず、『ヨハネの黙示録』というこの難解な一書をどのように読むか、ということですが、ここではやたら末端の象徴の意味付けや解読がどうとかいう以前に、これは『福音書』の並行宇宙なんだと思って読むのが良いと思います。地上で起こったことが『福音書』ですね。で、黙示録はその間天上界で何が対応的に起こっていたか、そしてこれから何が起こるかを書いているのだと。で、地上はこんな感じにツライだろうけど、天上界ではこんな具合に話が進んでるのだから耐えなさい、というわけです。
第一部というのはこの当時の小アジアの7つの主要教会へのメッセージです。ちゃんと見てんぞ、気を抜くなよ、ということです。これはヨハネの背後に現れたキリストの言葉、として書かれてはいますが、中身は結構具体的です。この黙示録が単なる終末の幻視を抽象的に描いたものではない、という点を知っておくためにもちょっと紹介しておきましょうか。
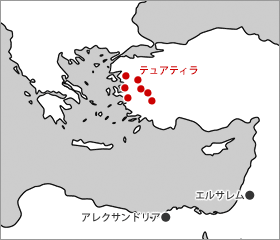
初期教会の分布
わたしはお前(テュアティラ教会)の[善き]行ないを知っており、お前の愛と信仰と奉仕と忍耐とを知っており、またお前の最近の行ないが初期の行いにまさっていることも知っている。しかしそれでも、わたしはお前に対して苦情を言いたいことがある。なぜなら、お前は女預言者だと自称するあの女イゼベルをそのなすがままにさせて、[そのため]あの女はわたしの僕に謝った教えを与え、まだ惑わして………
といった具合。
で、第二部の「2七つの封印」が、イエス以前のヘブライの民と現れた数々の預言者の時代と並行した物語、「3神の秘められた摂理の実現」がキリスト(イエス)の誕生から現在の(初期教団の)置かれている状況とその未来に並行した物語、という感じになると思います。いや、無論いろいろな読み方ができるようにできているのが教典ですから、あくまで一例ですよ?
これまでに見てきた、ヘブライ−イエスに至る思想の中核に「蛇の知恵」をめぐる革命があったという視点は、まさにこの「3神の秘められた摂理の実現」を読み解くための視点です。ですので、このパートを詳しく見ていくことになりますな。
んが、その前に。
このような「黙示」の系譜がどのように綴られてきたか、それがどんな由来に連なる書なのか、その辺りのことも押さえておきましょう。
黙示の系譜
大雑把に言いますと、「世界の終わり」というのは「オリエント1」に見たゾロアスターの思想がその根本にあり、それがヘブライの民に伝わってユダヤ教旧約聖書にある各種の黙示の書を形成した、ということになります。
ヘブライの民は何度か述べたように、巨大帝国化するバビロンに敗れ、「バビロン捕囚」を体験するのですが、このバビロンを倒して彼らが解放される契機となったのがペルシアの興隆でした。アケメネス朝ペルシアが新バビロニア帝国を撃破するのにあわせて、バビロンに連れてこられていたヘブライの民はエルサレムに帰還することができたのです。要するにペルシアは救い主だったのですね。「オリエント1」でも見たようにこのアケメネス朝ペルシアにあってゾロアスター教がどこまで流行っていたのかは謎なんですが、その後の状況から見て、この時点でヘブライへその思想の幾ばくかが流れ込んだのは間違いなさそうです。

バビロン捕囚
エルサレムに帰還すると、ヘブライの宗教指導者たちは、捕囚以前の緩かった信仰を改め、唯一ヤハヴェのみの信仰による厳しいユダヤ教を作り上げようと本格的な編纂を始めます。その際、バビロンによりエルサレムが崩壊した記憶を預言者による滅びの予告→エルサレムの凋落という形でイザヤなどはまとめていったのでした。そこで彼らが信仰を改めるから救ってくれと神に祈る様子は「オリエント2」で見ましたね。
これが「王の国」を示すラハブ・レヴィアタンというドラゴンを悪と成す思想だったことを思い出しましょう。さらに、成立年代がかなり「こちらより」(すなわち紀元前後より)となるので「オリエント2」で扱いませんでしたが、これらの捕囚以後のヘブライの民によって書かれた黙示の中で最も代表的なのが『ダニエル書』です。七十人訳聖書の方には、ここで早くも「ドラゴン封じ」が重要なモチーフとして描かれているのが要注目です(「ダニエル書補遺」マソラ本文からは外される)。
その後、前項に見るようにエルサレムの中心で体制化する主要派と、野に下って秘教的な独自の教義を発展させる「エッセネ派」などに分かれ、中でもエッセネ派は『死海文書』に見たように、ゾロアスター教の光と闇の勢力が戦う世界の終末と、その終末に現れる救世主(メシア)のイメージといった要素を多分に含んだ教義を成していたと考えられます。
そのエッセネ派からイエスが出たことからも分かるように、『ヨハネの黙示録』も、こういった「黙示の系譜」のひとつなのです。それはバビロンやエジプト(ラハブ)といった「王のコード」にヘブライの知恵が対抗しようとする物語でした。おそらくその点がゾロアスター教の思想に無い決定的な違いでしょうか。
しかし、系譜とは言っても『ヨハネの黙示録』にはそれまでの黙示の系譜とは一線を画するものがあります。黙示の系譜は「王のコード」の暴走を警告しはしても、具体的なその対抗策は示さなかった。それはイエスの時に形作られたのです。これまでに見てきたように、イエスはその「王のコード」に実際対抗してしまう方法を提示しました。生の概念をシフトし、死の概念をシフトし、王のコードが由来する蛇の知恵の及ばないポジションを人と人の関係が構築し得る、イエスはそのひな形を残したのです。
ここにおいて、『ヨハネの黙示録』の示すメッセージは、それまでの黙示の系譜が「神様が王のドラゴンを倒してくださる様、祈り、耐え忍びなさい」であったものから歩みを進め、「イエスのコードをもって王のコードを打ち破りなさい」というメッセージになったのです。それはそのままキリスト教がユダヤ教と異なり拡張する宗教となった由来そのものでしょう。
おそらくこの差が諸々の黙示と『ヨハネの黙示録』を読み比べる際の主たる眼目となるだろうと思います。
赤い巨大な竜
また、天に大きな徴が現れた。それは、太陽を[衣として]身にまとった女で、月を足の踏み台とし、その頭には十二の星の冠を戴いていた。女はその胎に子を宿しており、子を産もうとして、陣痛の苦しみで叫んでいる。また、もう一つの別の徴が天に現れた。それはほら、赤い巨大な竜で、七つの頭と十本の角を持ち、その頭には七つの王冠を被っている。竜の尻尾は天のもろもろの星の三分の一を掃き寄せて、それらを地上に投げ落とした。それから竜は、今まさに子を産み落とそうとしている女の前に立った。それは、女が子を産み落とすや否や、その子を呑み込んでしまうためであった。
−−−−−−ヨハネの黙示録
こうして『ヨハネの黙示録』は後半、現在進行形での信者たちの苦難と並行する象徴界の動向を語り始めます。その書き出しからしてもうズバリと言いますか、今まであーだこーだと言ってきたのはつまりこういうことです。
「蛇の知恵」の大将である「赤いドラゴン」が、その知恵を無効化する恐れのあるフォーマットを今まさに発動させようとしている「母(マリア)」と「子(イエス)」を呑み込もうとする場面から始まるのです。呑み込む、というのは殺すのではなく、「蛇の知恵」側へ染めようという意味です。この局面イエスは逃れますが、染められた「子」は、やがて第二の獣として姿を現すことになるでしょう。

赤い巨大な竜
この赤いドラゴンこそが「エデンの蛇」であり、人に(アダムの妻に)「蛇の知恵」をもたらした悪魔であり、後に見るようにそれは「王のフォーマット」の源泉なのです。
この太古の蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすもの、
−−−−−−ヨハネの黙示録
ということですね。悪魔とサタンが別途記述されるのはこの時代のユダヤ教間では悪魔が「ベルゼブル」とされることが多かったからでしょうか。『福音書』ではこの「ベルゼブル」がユダヤ教側の人たちの間で標準的に使われます。「ベルゼブル」というのは「オリエント2」のウガリット神話で見た「バアル神」のこと。ダビデ−ソロモン時代のヘブライの民にもファン(?)が多かったのですが(ソロモン宮殿はバアル神殿の様式で建てられたともいいます)、その後ヤハヴェ信仰が巻き返す過程で「バアル神を信仰するような輩は悪魔の手先」ということになりまして、凋落します。バアルと音の近い「蝿」でそれを示してバカにしまして、これを「蝿の王・ベルゼブル」と言いました。
[逃げる]女の後ろから、蛇は川のように水をその口から吐き出した。女を奔流で押し流そうとしたのである。すると、大地が女を助けようとその口を開き、竜がその口から吐き出した川を飲み干した。そこで、竜は女に激怒して、彼女の子孫の残りの者たち、すなわち、神の誡めを守り、イエス[について]の証言を堅持している者たちと戦うために出て行った。
そして、竜は海辺の砂浜に立った。
−−−−−−ヨハネの黙示録

ドラゴンと母(マリア)
こうして母(マリア)は地上で匿われ、「蛇の知恵」によらない出産を行います。おそらくは史上初の「アンチドラゴンコード」による子供の誕生ですね。ドラゴンが激怒するのも宜なるかな。彼は救世主(キリスト)として世に「福音」を授けることになりますが、ドラゴンの方は子を奪うことができなかったために、その知恵を二匹の獣に授け、地上に覇を称えさせることになります。
二匹の獣
その獣は十本の角と七つの頭を持っており、その角の上には十の王冠を戴き、またその各々の頭には神を冒涜する[さまざまな]名前が記されていた。わたしが見た獣は、姿は豹に似ていたが、その足は熊の足のようで、その口はライオンの口のようであった。
−−−−−−ヨハネの黙示録
それで、全地は驚愕して獣の後に[従った]。このような権威を獣に与えたのは竜であったから、人々は竜を礼拝した。また、「誰がこの獣に匹敵しようか。誰がこの獣に戦いを挑むことができようか」と言いつつ、この獣をも礼拝した。
(中略)
また、あらゆる部族や国民や国語[の違う民]や民族を支配する権威が与えられた。地上に住む者たち、すなわち、世界が創造された時から、屠られた小羊の命の書の中に名前の書き込まれていない者たちは皆、この獣を礼拝するようになる。
−−−−−−ヨハネの黙示録
ということです。赤いドラゴンによる「蛇の知恵」はこうして「王のフォーマット」へ接続するのです。この第一の獣は良く言われるようにローマの歴代の皇帝を暗示しますが、それだけではなく広く「王一般」を示すものと考える方が良いでしょう。そのバックグラウンドには、「オリエント2」で見た王のふるう非対称性の力と欺瞞としての対称性の知恵と、それらを糾弾したヘブライの知恵の歴史が凝縮されていると見るべきです。

地上の王に王権を授ける第一の獣
そして、この第一の獣に続いて第二の獣が姿を現します。
またわたしは、もう一匹別の獣が地中から上がって来るのを見た。その獣は、小羊[の角]に似た二本の角を持ち、その語り様は竜が吠えるようであった。この[第二の]獣は、第一の獣の面前で、かの獣が持っていたすべての権威を振るい、地と地上に住む者たちとが、致命的な傷の治った、彼の第一の獣を礼拝するように仕向ける。この獣は数々の大いなる徴を行い、人々の[見ている]前で、火を天から地上に降ろしさえする。
−−−−−−ヨハネの黙示録
羊・小羊というのは全面的にキリスト(イエス)を示します。ですのでこの第二の獣というのは「キリストのような振る舞いをする偽預言者」を現わしています。この頁はじめの聖女マルガレタの所で述べたように、悪魔はキリストに化けて囁くものなのですね。『福音書』の中でもイエスは再三にわたって、そのような偽預言者が現れることに注意を促しています。

悪魔に操られる偽預言者
このあたりは「ドラゴンのコード」と「アンチドラゴンのコード」の境界を見極めることの難しさを示しているのかもしれません。なんと言っても数万年に渡って人々は「蛇の知恵」の上に生活を築いてきたのでして、そちらに耳がなじみやすい、というのはキリスト教を立ち上げようという彼らにも重々承知のことであったと思われます。
さて、こうして地上に「王のコード」による覇権がなったことが示されるのですが、要するにいわゆる「←今ココ」ということですね。そして、この先どうなるのか、どうなるべきなのかが以下描かれます。キリスト者はこの「王のコード」に耳を傾けてはならない、「イエスのコード」をもって貫きなさい、と。その光景がこうです。
また私は見た、すると小羊がシオンの山の上に立っていたではないか。小羊と共に、十四万四千人の人々も[立っていたが]、その人々の額には小羊の名前と小羊の父の名前とが書かれていた。
(中略)
これらの者たちは、女と[交わって]身を穢したことのない人々である。彼らは童貞を保っていたからである。これらの人々は、小羊がどこへ行こうと付き従っていく従者たちである。
−−−−−−ヨハネの黙示録
童貞というのは処女の重視で見たのと同じものを示します。結局続くキリスト教の本線では禁欲的であることのみが大きく取り上げられてしまいましたが、その本質は「やるのやらないの」ではなく、ジーンによる共同体の基盤(血縁家族)を脱し、ミームによる基盤の構築を行え、というイエスの思想です。
そのリフォーマットによる社会の在り方のみが、人の世界全体の「脱ドラゴン」を成す、というイエスの考えは上に見ましたが、それが難しいのもまたそこに書いた通り。
大淫婦と獣
さて、一方でこの「蛇の知恵」が太古からの大地母神のイメージと密接な関係があることもこれまでに繰り返し述べてきました。ここでですね、上に見た「赤いドラゴン」「二匹の獣」を「赤いドラゴン−悪魔−大地母神」と変換しまして、その両脇に「二匹の獣(地上の王)」を配しますと、このあたりに大きく影響した大地母神の原イメージ、北アナトリアはプリギュアの地に見たキュベレーの像になります。

母神キュベレー
そしてこのイメージは『ヨハネの黙示録』が語る次のイメージへと接続します。
[そこで]私は一人の女が緋色の獣の背に座っているのを見た。その獣は、神を冒涜する数々の名前が体中に書かれていて、七つの頭と十本の角とを持っていた。この女は紫の衣と緋色の衣とをまとい、金と宝石と真珠とで身を飾り立てて、その片方の手には忌まわしいものと彼女の淫行の[もたらした]穢れとが一杯に満ちている金の杯を持ち、その額には、一つの名前が書かれていた。[その名前には、]秘められた意味[が込められていて]、「大いなるバビロン、淫婦どもと地上の忌まわしい者どもとの母」というものであった。
−−−−−−ヨハネの黙示録
あなたが見たかの女は、地上の王たちを統治する大いなる都のことである。
−−−−−−ヨハネの黙示録
先に、
これを糾弾し、ヘブライの民はドラゴンを悪と見立てて神に討たせたのでした。つまり、旧石器時代の大地母神に由来する「多くが生まれ出る」コードに、圧倒的な非対称性の力・技術を振う「王」が接触すると怪物化してしまう、ということです。実際、古代オリエントは歯止めのかからぬ帝国の膨張という現象がバビロンから、ペルシアから、マケドニアから、ローマからと次々起こり、幕を閉じることになります。
と書きましたが、このオリエント千年の王の怪物化の模様そのものを「大淫婦バビロン」として示しているのですね。

大淫婦バビロン
このイメージこそが「マリアの対極」です。それは小アジアからギリシアにおいて「王を生み出してきた」女神たちにほかなりません。「大淫婦」というひどい表現で次々と地上の王と交わり、そして次々と次なる地上の王を生み出してきたことを示しますが、これがもとより堕落した風紀紊乱な大都市、という倫理的なコードを示すのに止まらないことは明らかでしょう。これは「王のフォーマット」が王を生み出すシステムそのものをいっているのです。
以上、『ヨハネの黙示録』そのものからの引用を主軸に述べてきましたが、最早くどくど言わなくてもこの一連の表現が「オリエント」からずっと見てきた「ドラゴンのコード」と「アンチドラゴンのコード」のせめぎ合いを書いているものであることはお分かりでしょう。ヘブライの知恵からイエスのコードによって示されるキリスト教の深層というのはこういうものなのです。
おわりに
キリスト教とその母体となったユダヤ教が一神教という発明により、それまでの多神教において活躍していたモンスターたち、殊にドラゴンを封じ、自然への畏怖から人間主体への視点へシフトしたことが後の産業革命という生きものとしての人間自身を窮地に追いやるテクノロジーの暴走を生み出した。
この様に語られる思想の問題点は、これまでに見た「王の由来」とその欺瞞への糾弾というヘブライの知恵の本質を見逃していることです。一神教が暴走を生み出すのではないのです。少なくとも「王を怪物化させる」のは多神教の知恵の方なのです。これはキリスト教が敷衍し、それからの中世ヨーロパの何が暴走したのかと問うてみれば分かります。暴走の要因は『ヨハネの黙示録』がラストに描くように、一時封じられたのです。
私はまた、かの獣と地上の王たちとその軍勢とが、馬に乗った騎士とその軍勢とに戦いを挑むために、結集しているのを見た。しかし、獣は捕らえられた。またこの獣の面前でもろもろの徴を行って、獣の刻印を受けた者たちや獣の像を礼拝する者たちを惑わしたかの偽預言者も、獣と一緒に捕えられた。これらの両者は、生きながらに、硫黄の燃えている火の池に投げ込まれた。
−−−−−−ヨハネの黙示録
また私は、一人の天使が、底なしの深淵の鍵と大きな鎖とを手にして、天から降って来るのを見た。そして、竜、彼の太古の蛇−−これは、悪魔またサタンのことである−−をつかまえ、一千年間縛った。そして、その竜を底なしの深淵に投げ込んで錠をおろし、その上に封印した。一千年の期間が終わるまで、竜がもはや諸民族を惑わすことのないためである。一千年の後に、竜は短期間解き放たれるはずである。
−−−−−−ヨハネの黙示録
そう、暴走の原因「蛇の知恵」は赤いドラゴンとともに封じられました。この頁に見てきた「イエスのコード」は一定の成果を見せ、ヨーロッパはかつてのオリエントの王たちのような膨張を示すことなく中世を生きていきます。
が、驚くべきことに最後の預言が示す通り、「一千年の後に、竜は短期間解き放たれる」のです。
オリエントの地を離れ、キリスト教が広まっていく地域は、それまでの中東の地とは違う「黒森の地」でした。そこには砂漠の民には想像もつかないような「生い茂る自然」をバックグラウンドに生活する人々とその信仰があったのです。その地では大地の竜蛇ははるかに活き活きと蠢いており、その姿をわれわれは次頁に見ていきます。
また、イエスは「それ以上は悪魔が言わせるのである」と釘を刺しましたが、口を閉じられない人というのはたくさんいたのです(笑)。キリスト教の広がる背後にあって、その「我慢できない人たち」は「逆に考え」ました。
「蛇の知恵」を極限まで持っていったらどうなるのか?
それがキリスト教の「後戸の神」です。その対極を行く知恵が「黒森の地」に生きる竜蛇たちと接触し、静かな中世ヨーロッパの地下で繁殖を続けました。そのドラゴンは預言の通りに解き放たれることになるでしょう。
この「後戸の神」の知恵を「グノーシス(叡智)」と言います。イエスのコードを食い破るこの知恵の怪物が近現代の膨張のトリガーとなるのです。われわれは龍の旅の最後に、このグノーシスの蛇、ウロボロスが世界を巻き込む様を見ていくことになるでしょう。

ウロボロス

 目次へ
目次へ 中国
中国 『黄金伝説』のドラゴン
『黄金伝説』のドラゴン
 ページの先頭へ
ページの先頭へ



 この項目へ
この項目へ